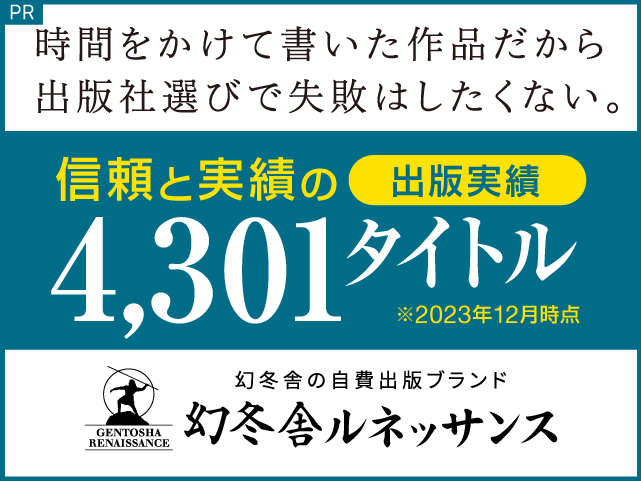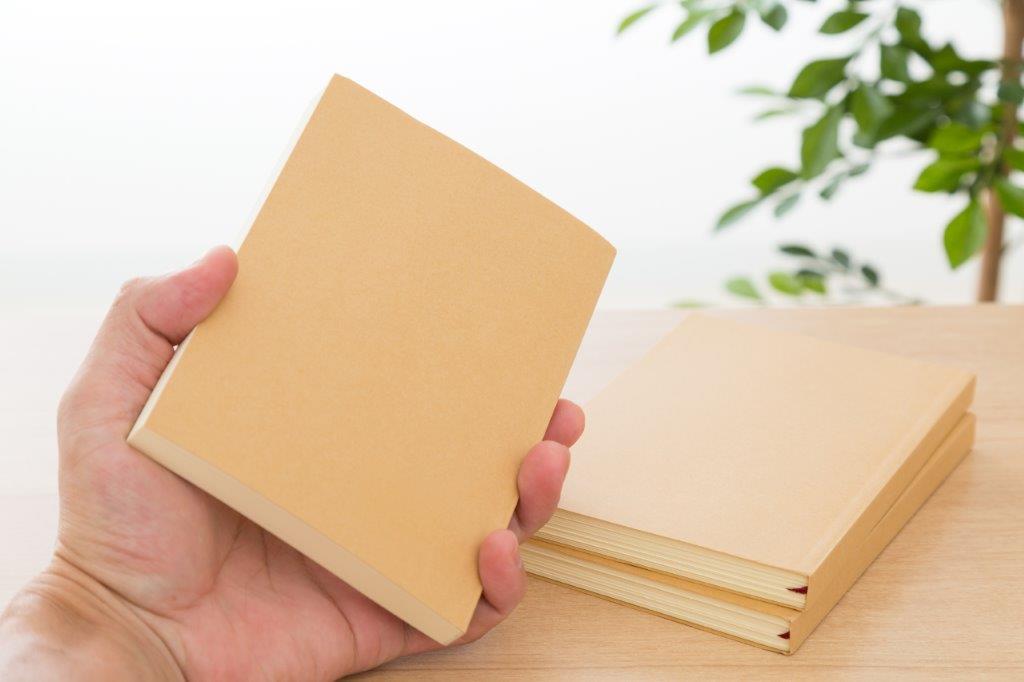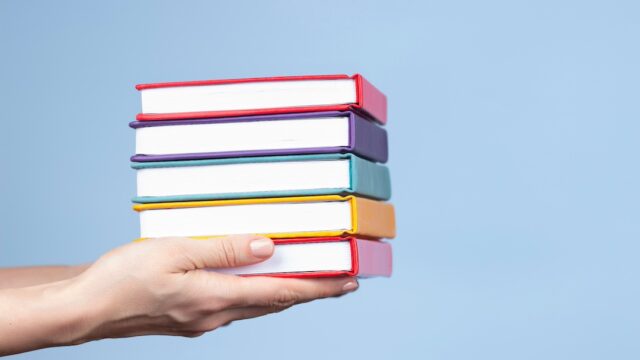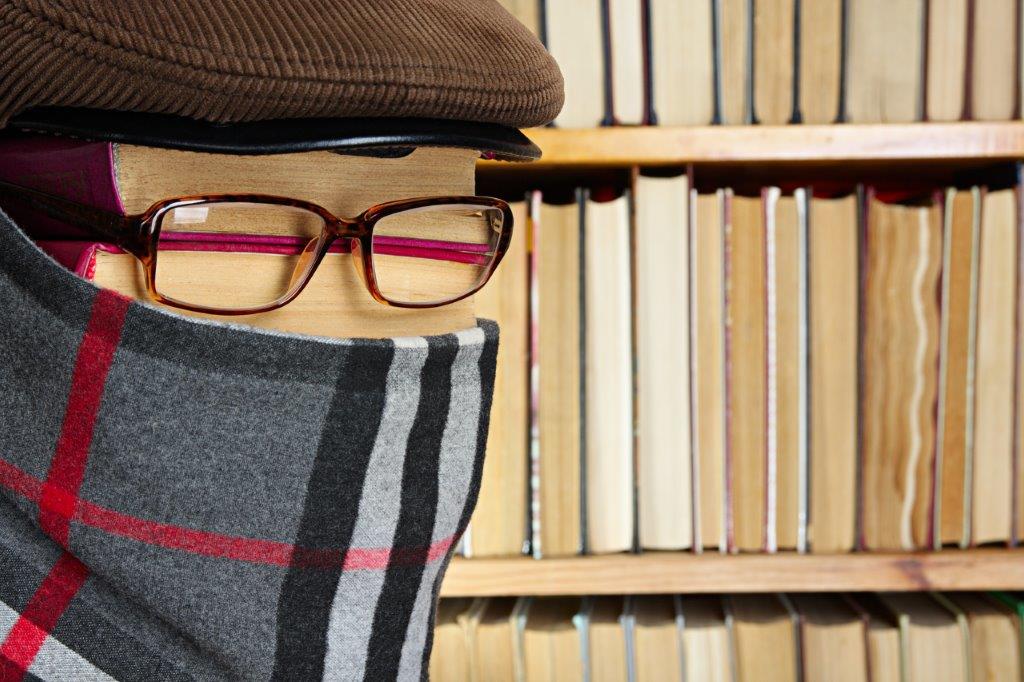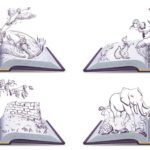エッセイの書き方や注意点とは

「エッセイを書いてみたいけど書き方がよくわからない」「エッセイがうまくまとまらない…」など、エッセイの作品に興味がありつつも、わからないことが多くてなかなか踏み出せない、原稿が進まない、と悩む人は多いようです。
そこで、今回は「エッセイ」の書き方について詳しくご紹介します。ぜひ、今回の記事を参考にしながら素敵なエッセイを書いてみてくださいね。
エッセイとは
そもそも、エッセイとはどのようなものなのでしょうか。
エッセイとは、自分の意見や想いなどを自由な形式で書き連ねたものです。「随筆」「随想」などとも呼ばれますが、ルールに縛られることなく、自分を表現できるのが特徴です。「コラム」と混同されることも多いのですが、コラムの場合は形式が決まっているため、エッセイと比較すると自由度に欠けます。
「何にも縛られずに自分の気持ちを書きたい」という方は、コラムよりもエッセイの方が適しているでしょう。
エッセイの書き方のポイント
では、エッセイはどのように書けばよいのでしょうか。具体的な書き方のポイントについてご紹介します。
テーマを決める
まずは、テーマを決めることから始めてみましょう。自分の意見を述べるだけのエッセイにするのか、何らかの物事に対しての想いを載せるのか、想定する読者は誰なのかなど、何をテーマにして書くのかを決めることで執筆する内容がイメージしやすくなります。
いきなり本文に入る前に、テーマを決めてある程度記載する内容を絞っておきましょう。
構成を考える
構成を考えることもエッセイを書くうえでは重要な作業です。エッセイを書く以上、本の向こうには読者がいるわけですから、読者がわかりやすい、面白いと思えるような構成を組み立てる必要があります。
中には構成を組み立てずに本文を執筆する方もいますが、この方法では思わぬ方向に話が進んでしまったり、取り入れたいと思っていたエピソードをうっかり忘れてしまったりなど、トラブルが起きやすいため注意が必要です。
短い文章からスタートしてみる
突然長文を書き始めるのではなく、構成ごとに数行にまとめて書き上げていってみましょう。絶対に必要なエピソード、取り入れたいワードなど、メモ程度で問題ないので、構成ごとに作成しましょう。
可能であれば5~10行ずつにまとめて書くと、いざ本文を作成する際に内容に肉付けしやすく、より深みのある文章になりやすいです。
エッセイを書く際に陥りやすい注意点
プロ・アマ問わずにエッセイを書く方は多いですが、書きなれていない方がエッセイを書くと、どうしても陥ってしまう問題が2つあります。エッセイの作成に躓いてしまう原因でもあるので、注意点を参考にしてみましょう。
取捨選択ができていない
まずは、内容の取捨選択ができていないというケースがあります。起きた出来事をそのまま書いたり、会話のやりとりも余すことなく書いたりなど、エッセイを書きなれていない人ほど「情報を詳細に書こう」としてしまいます。
確かに、詳細を書くことでわかりやすくなるケースもありますが、これでは一つのエピソードが長くなり、話のテンポが遅くなってしまう傾向にあります。必要な部分をつまみ出し、不必要であると判断できる内容は削除することで、読みやすいエッセイになります。
淡々と出来事だけを記載している
エッセイを日記のように書いてしまう方もいます。どこで誰と何をしたのか、という情報は確かに必要ですが、そこからさらに「その時に思ったこと・感じたこと」のように、心の中を表現することも大切です。
エッセイは自分の中身を表現するものでもあるため、日記感覚になりすぎないよう注意しましょう。
エッセイは決して難しいものではありません。いくつか書き方と注意点を把握しておくことで、魅力的なエッセイが作成できます。初めてエッセイを書く人は、今回の記事を参考にしながら世界に一つだけの素敵なエッセイを作ってくださいね。