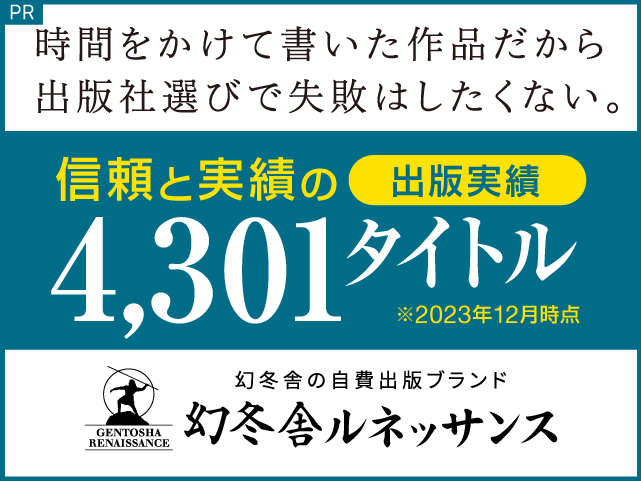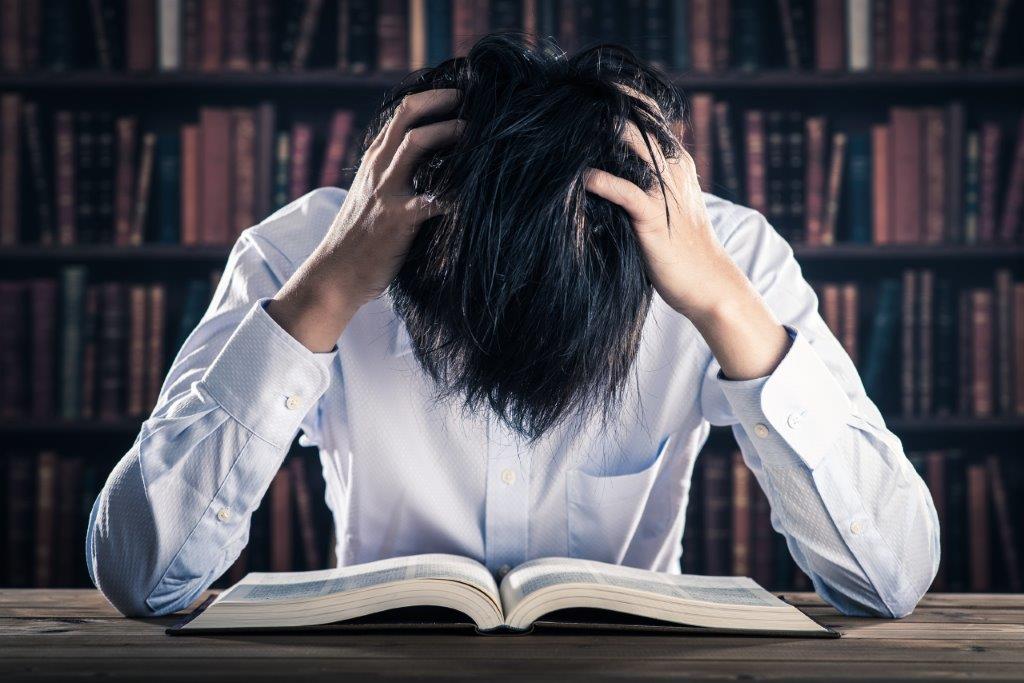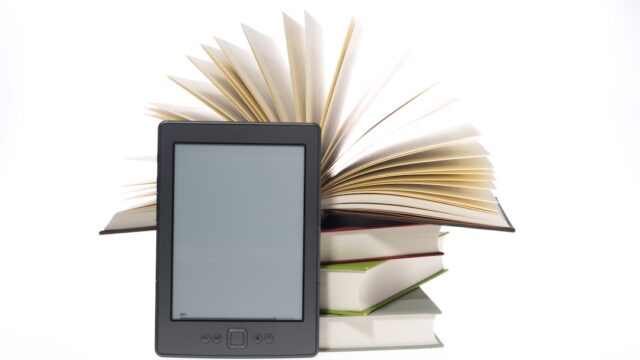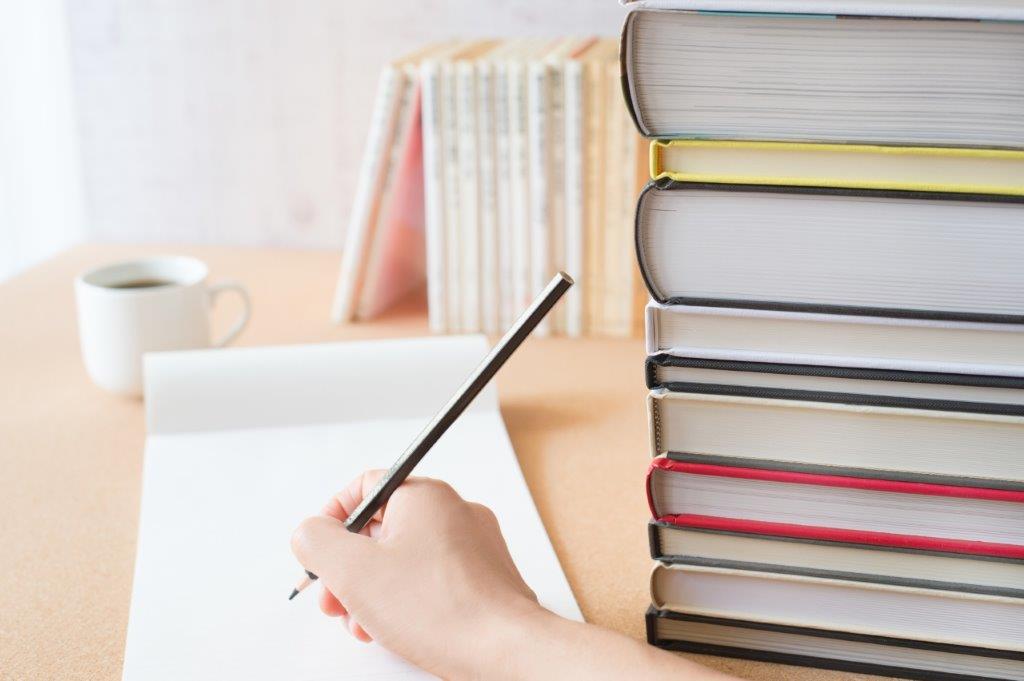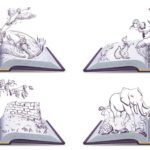意外と難しい社史のタイトル設定、構成の組み立て方

社史を作成するうえで重要視されるのは「内容」です。時間をかけて資料を集め、何度も書き直しながら原稿を作成する。こうして内容を充実させるのはもちろん、社史の制作に大切なことです。
しかし、重要視すべきなのは「内容」だけではありません。「社史のタイトル」や「構成」も、内容と同様に重要なポイントです。そこで、今回は社史のタイトル選定と、構成の方法についてご紹介します。
未来に残る社史のタイトル選定
社史のタイトルは、その社史を表す重要なポイントです。だからこそ、こだわる必要があります。例えば「○○社 社史」や「○○社のあゆみ」といったタイトルでは、シンプルすぎますし、読み手の心には響かないでしょう。その会社らしさ、もしくは社員へのメッセージ、社外へのメッセージなど、読み手を想定してオリジナリティ溢れるタイトルを選定することが大切です。
例に挙げた「○○社のあゆみ」というシンプルなタイトルでも、メッセージ性を込めたサブタイトルをつけるだけでも印象はだいぶ変わります。また、会社の歴史を決定づけた創業者の一言や、代表的な商品のキャッチコピーをそのまま社史のタイトルにする、というアイデアもあります。
魅力的なタイトル選定によって、未来に残る社史になることは間違いありません。
全体の構成を考えるポイント
社史の中身をさらに魅力的にするには「構成」を考えなくてはなりません。ただ事実を淡々と記しているだけでは、読み手が飽きてしまいますし、興味を引き付けることも難しいです。
構成を考える際のポイントについて見てみましょう。
基本の構成
まずは、基本の構成を頭に入れておくことが大切です。「会社の歴史」「記録」「情報発信」などの分野を大きくとり、社史に掲載します。昔ながらの一般的な社史の構成で、基本的な情報を余すことなく記載できます。
他社の社史を参考にする
他社の社史を参考にするのも、構成を考える際のヒントになります。会社によってその雰囲気が大きく変わる社史は、自社らしさをアピールするうえでも参考になるもの。最近は、web上にアップしていたり、配布していることもあるので、可能であれば他社の社史をチェックしてみましょう。
社史の方向性、ジャンルから考える
社史の方向性から構成を考えるのもおすすめです。例えば、ユニークな社史にするのであれば、堅苦しさを感じないようバラエティに富んだ社史の構成を組み立てたり、社員教育用に社史を作成するのであれば、会社の理念、方向性、目的・目標などを大きく取り上げてみるなど、社史の方向性やジャンルから構成を考えてみましょう。
重要なのは「本文」
どれだけタイトルが魅力的であっても、構成の組み立て方が完璧であっても、そもそもの本文が充実していなければ、せっかくの社史が台無しです。作成するにあたり、どのようなことに意識すべきなのでしょうか。
事実を記載しているか
当然ですが「事実を記載している」ということが大前提です。誤った内容を記していないか、徹底的に確認しなければなりません。特に「年号」「経営状況」などのような、数字を用いた内容は誤りやすいため、作成時には注意が必要です。
読み手に向けたメッセージになっているか
社員向け、広報向けなど、読み手に向けたメッセージになっていることも大切です。単純に、自社の情報を淡々と記すような独りよがりな社史になってしまうと、読み手に関心を抱いてもらうことは難しいでしょう。どのようなメッセージを送りたいのかをあらかじめ考えておき、それをコンセプトとして作成すると良いでしょう。
社史の作成で難しいのは、原稿作成だけではありません。「タイトルの設定」「構成の組み立て方」なども難しく、とても時間がかかるものです。会社の社史をどのように活用するのか、誰に向けた社史なのかを今一度考えて作成することが基本です。ぜひ、今回の記事を参考にしながら魅力的な社史の作成を目指してみましょう。